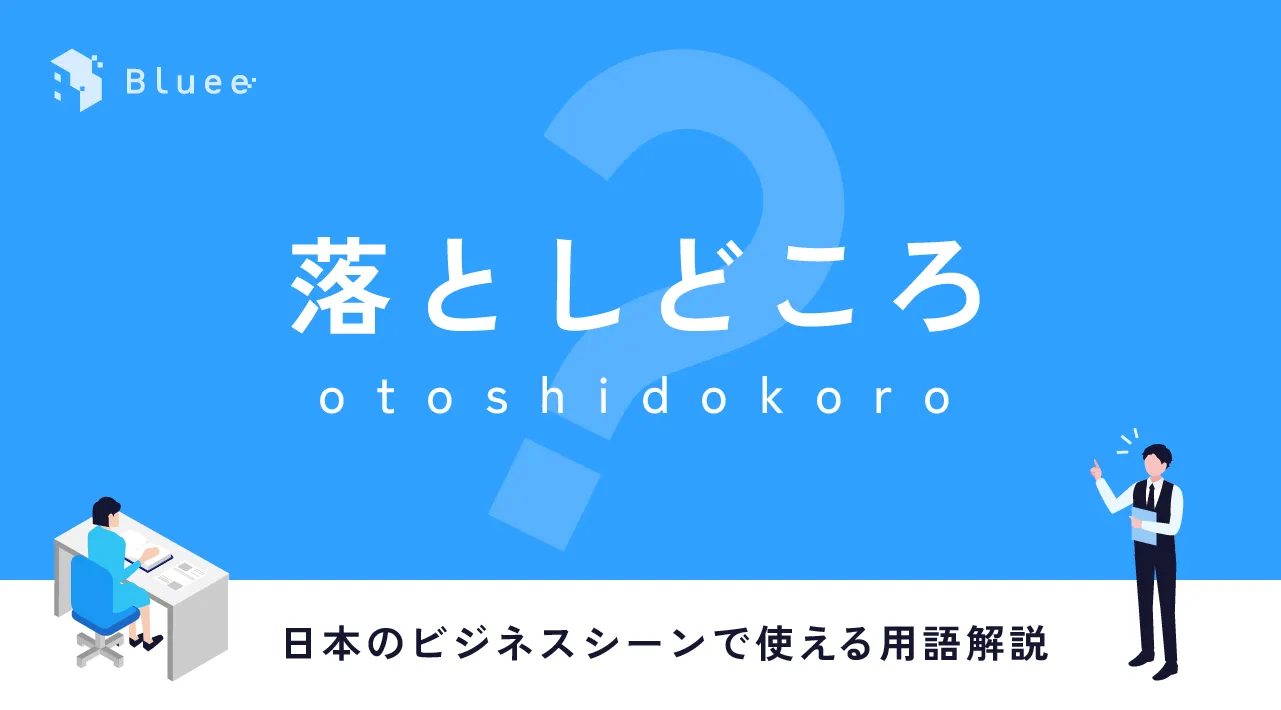日本のビジネスシーンでは、意見や案が対立した時に、それぞれのいいところを取ってまとめた案を「折衷案(せっちゅうあん)」と呼びます。
この記事では、「折衷案(せっちゅうあん)」の意味や使われ方、注意点などを解説します。
「折衷案(せっちゅうあん)」の意味
「折衷案(せっちゅうあん)」の基本的な意味
「折衷案(せっちゅうあん)」は「折れる(おれる)」と「真ん中(まんなか)」を組み合わせた言葉で、複数の意見や案のいいところを取って、真ん中あたりにまとめた案という意味です。
英語では“compromise”
韓国語では“절충안”
ミャンマー語では“နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် အကြံဥာဏ်”
と表現されます。
「折衷案(せっちゅうあん)」がよく使われる場面
「折衷案(せっちゅうあん)」がよく使われる場面は、以下のとおりです。
- 会議や打ち合わせで、意見が対立した時
- プロジェクトや業務の進め方について、複数の案がある時
- 顧客や取引先との交渉で、合意点を見つけたい時
「折衷案(せっちゅうあん)」の具体的な使用例
以下に、「折衷案(せっちゅうあん)」の具体的な使用例を紹介します。
例文1:「プロジェクトの進行方向について意見が分かれたので、折衷案を考える必要があります。」
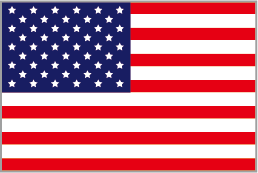 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“As opinions regarding the direction of the project have diverged, it is necessary to consider a compromise solution.”
 韓国語で意味を確認!
韓国語で意味を確認!
“프로젝트의 진행 방향에 대한 의견이 분분하므로 타협안을 생각해야 합니다.”
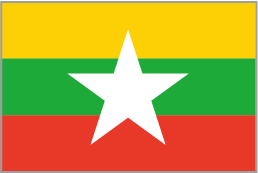 ミャンマー語で意味を確認!
ミャンマー語で意味を確認!
“ပရောဂျက်ကို ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမှာ အမြင်မတူတာကြောင့်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် အကြံဥာဏ်တစ်ခုကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။”
例文2:「折衷案を提案することで、チーム内の対立を解消することができました。」
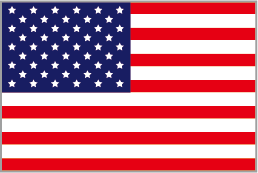 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“Introducing a compromise proposal allowed us to settle disagreements within the team.”
 韓国語で意味を確認!
韓国語で意味を確認!
“절충안을 제안함으로써 팀 내의 대립을 해결할 수 있었습니다.”
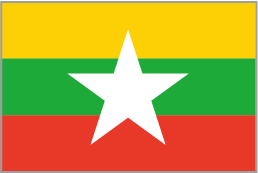 ミャンマー語で意味を確認!
ミャンマー語で意味を確認!
“နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် အကြံဥာဏ်တစ်ခုကို ရှာဖွေပြီး အဆိုပြုလိုက်တဲ့အတွက်၊ အဖွဲ့ထဲက ငြင်းခုံမှုတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။”
例文3:「新しいマーケティング戦略について、折衷案を採用することに決定しました。」
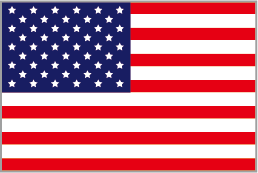 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“We have decided to adopt a compromise solution for the new marketing strategy.”
 韓国語で意味を確認!
韓国語で意味を確認!
“새로운 마케팅 전략에 대해 절충안을 채택하기로 결정했습니다.”
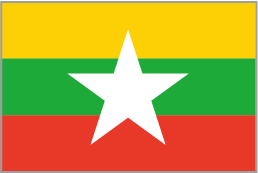 ミャンマー語で意味を確認!
ミャンマー語で意味を確認!
“ထုတ်ကုန်အသစ်ရောင်းချရေး မဟာဗျူဟာအတွက်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် ရလဒ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။”
「折衷案(せっちゅうあん)」を使用する際の注意点
「折衷案(せっちゅうあん)」は、複数の提案から良い点を組み合わせて新たに作り出される案です。この手法は最善とは限らないものの、関係者の意見が反映されるため、お互いの合意を得るのに効果的です。ただし、使われ方によっては「妥協案」や「落としどころ」といったニュアンスを持つこともあるため、意図が誤って伝わらないように使い方には注意が必要です。
「折衷案(せっちゅうあん)」の言い換え・類語
「折衷案(せっちゅうあん)」の言い換え・類語としては、以下のようなものがあります。
妥協案(だきょうあん)
「妥協案(だきょうあん)」は、対立する意見や要求の一部を譲歩し、双方が受け入れられる中間的な解決策を指します。主に交渉や議論の場で、双方の利益を考慮して合意を目指す際に用いられます。
例文1:「このプロジェクトの予算について、各部門の要望を考慮した妥協案を提案しました。」
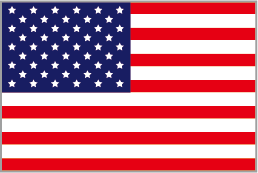 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“I proposed a compromise plan that takes into account the demands of each department regarding the project budget.”
例文2:「顧客との契約内容について、双方が納得できる妥協案を見つけることができました。」
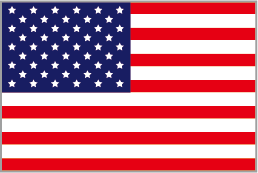 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“We were able to find a compromise solution that both parties are satisfied with regarding the contract details with the client.”
譲歩案(じょうほあん)
「譲歩案(じょうほあん)」は、対立する意見や要求に対して、一方が自らの要求を一部譲ることで合意に達するための提案を指します。特に、交渉や調整の場で、自分たちの利益をある程度犠牲にしてでも合意を目指す際に使われます。
例文1:「営業部からの譲歩案を受け入れることで、スムーズに交渉が進みました。」
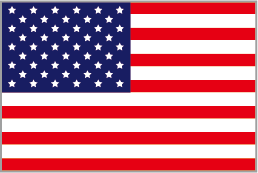 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“By accepting the concession proposal from the sales department, the negotiations proceeded smoothly.”
例文2:「取引先との意見の食い違いを解消するため、譲歩案を提示しました。」
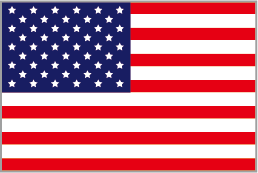 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“To resolve the disagreement with our business partner, we presented a concession plan.”
中間案(ちゅうかんあん)
「中間案(ちゅうかんあん)」は、対立する複数の意見や提案の間を取り持つ形で、双方にとって受け入れやすい中間的な解決策を示す提案を指します。意見の衝突を避けつつ、バランスを取るために使われます。
例文1:「会議で出された中間案が、全員の合意を得ることができました。」
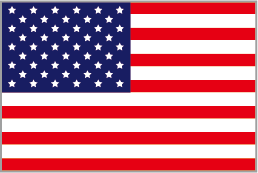 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“The intermediary proposal presented at the meeting was able to gain consensus from everyone.”
例文2:「A案とB案のどちらもメリットがあるため、中間案を検討することにしました。」
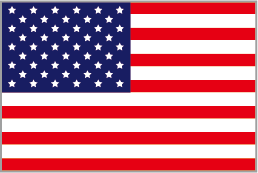 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“Since both Plan A and Plan B have merits, we decided to consider an intermediate proposal.”
落としどころ(おとしどころ)
「落としどころ(おとしどころ)」は、対立する意見や利害の調整において、双方が最終的に合意できる妥協点や解決策を指します。特に、意見が対立した場合に、納得できる解決策を見つけることが求められる場面で用いられます。
例文1:「長時間の議論の末に、全員が納得できる落としどころを見つけました。」
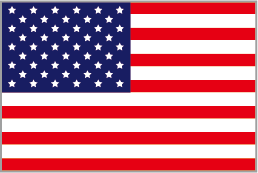 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“After lengthy discussions, we found a compromise that everyone could agree on.”
例文2:「この件については、双方が歩み寄れる落としどころを探す必要があります。」
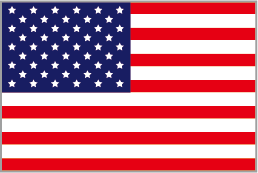 英語で意味を確認!
英語で意味を確認!
“We need to find a compromise that both parties can agree to regarding this matter.”
※「落としどころ」についてより詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
落としどころ(おとしどころ)とは?日本のビジネスシーンで使える用語解説
本記事では、日本のビジネスシーンで使えるビジネス用語「落としどころ(おとしどころ)」について、その意味や使われる場面、具体的な例を紹介します。
まとめ
「折衷案(せっちゅうあん)」は、日本のビジネスシーンでよく使われる言葉です。正しく理解して使いこなせるように、ぜひ覚えておきましょう。
事務局代行とは、イベントやプロジェクトの運営をサポートするために外部の専門組織が事務的な業務を代行するサービスです。ここからは、事務局代行サービスで使える日本語を紹介します。
表彰式(ひょうしょうしき)
「表彰式」とは、企業や団体が特定の個人やグループの業績や貢献を称えて、賞や感謝状を授与するイベントです。事務局代行では、表彰式の企画、招待状の送付、会場の手配、当日の運営などをトータルでサポートします。
英語では “awards ceremony” と表現されます。
周年イベント(しゅうねんいべんと)
「周年イベント」とは、企業や団体の設立記念日を祝うために開催されるイベントです。これは企業の歴史や成長を振り返り、将来への意気込みを示す場でもあります。事務局代行では、周年イベントのコンセプト設計、プログラムの企画、会場設営、当日の進行管理を一括して対応します。
英語では “anniversary event” と表現されます。
社員総会(しゃいんそうかい)
「社員総会」とは、企業の全社員が集まって経営方針や業績報告、今後の戦略などを共有する会議です。社員の意識統一やモチベーション向上を図る重要な機会です。事務局代行では、社員総会の準備、会場手配、資料作成、当日の運営サポートなどを提供し、スムーズな進行をサポートします。
英語では “general meeting of employees” と表現されます。
事務局代行について詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。